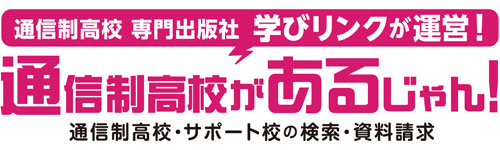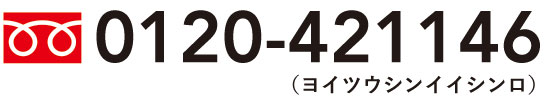椎名雄一先生コラム『不登校に効く心理学の話』60
通えている=大丈夫ではないので注意
2025年4月15日
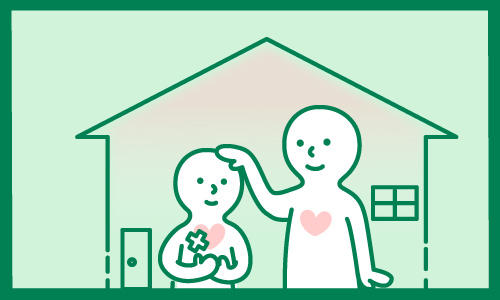 |
日々皆さんとメッセージのやりとりをさせていただいたり、カウンセリングをする中で気づいたことなどをこのコーナーでお伝えしています。
こんにちは、カウンセリング室の椎名雄一です。
新学期・新年度が始まり少し立った頃かと思います。昨年度まで不登校だったり、不登校気味だったお子さんが学校に通い始めると「もう大丈夫」と思ってしまいますが、ここでもう少しだけ慎重になってください。
「学校に行く」というアクションは親や先生から見たら1つのアクションに見えるかもしれません。
でも、調子が悪かったお子さんから見たら「朝起きる」「服を着替える」「靴を履く」「家を出る」「歩く」「人とすれ違う」「安全なトイレを探して入る」「先生やクラスメイトと関わる」「あいさつをする」「雑談にこたえる」「退屈なのを我慢する」「英語の遅れを嘆く」「体育のペアが決まらない」「忘れ物をして困る」「助けを求められずにとまどう」・・・ということ全てです。
今日は人混みに入ったら苦しかった。授業で居心地がすごく悪かった。クラスメイトの声を聞いていたら心がザワザワしてしまった。
そんなことを繰り返しながら、今日は48点、、今日は52点、、、と決して100点満点ではない1日を繰り返す。それが4月の学校かもしれません。
「友だちができた」も同じです。友だちは常に安心できる味方とは限りません。急に仲間外れになることもあるかもしれませんし、無理に話を合わせないといつうまくいかなくなるかわからない中で慎重に慎重に関わっているのかもしれませんね。それなのに「友だちができたからもう安心」というのも違いますね。
そんな試行錯誤を繰り返しているのが4月
場合によっては「明日はもう無理かもしれない」と思ってからも頑張って頑張って通っている可能性もあります。
僕も高校を経営していてよく目にするのが久しぶりに登校した生徒に「通えたね」というと「それを当たり前にしないで」と釘を刺される場面です。野球選手がホームランを打った後に「次も当然ホームランだよね」と言われたくないのに似ています。必死に軌跡を繰り返して達成したものを当然と言われたら息苦しくなってしまいますよね。
それでは家ではどんな助けができるでしょうか?
「行きなさい」という指示は出す方は簡単ですが、その後のことを考えていないので、お子さんが求めていない限りはおそらくあまり助けになっていません。
お子さんが学校に行けないのは自信がないからだったり、テンションが低いからだったりするわけですから、「行きなさい」と言って主体性を奪ったり、(あなたは信用できない)という無言の圧力をかけたりすれば当然、自信をなくし、テンションが下がります。
であるよりも日々の天気の話や食事、ゲームやアニメの話で盛り上がって、自信を高めて、テンションを上げてあげたほうが成功率が高まります。
「学校どうなの?」と聞いて「先生に話しかける勇気が出ない」と言われても親は助けることができません。それならば、先生に話しかける勇気が出るほど調子に乗せてあげたほうが助けになります。つまり、学校の中で「英語」「トイレ」「雑談」・・・なにで引っ掛かっているのかを聞き出しても実践的ではないアドバイスをするくらいしかできないのです。逆に何で困っているのかを知らなくても自信を高めてあげれば、自分で問題を解消できる確率が上がります。
4月は大人からは見えない小さいダメージがチクチクチクチクとお子さんにたまって行きます。
家では絵を描くのに夢中になったり、(ちょっとおかしなことを言っていても)自信満々に何かの解説をしてくれたり、おしゃべりを楽しんだりしてそのチクチクを抜けるといいですね。
学びリンクカウンセリング室では「保護者ラボ(ほごらぼ)」という名称で不登校のお子さんを持つ保護者の会を運営しています。約2,000人の保護者がオンラインで日々助け合っていますので保護者の皆さんご自身が不安になったり、焦ってしまったらお子さんに気づかれる前にSOSを投げかけて大人同士で解消するようにしてみてください。