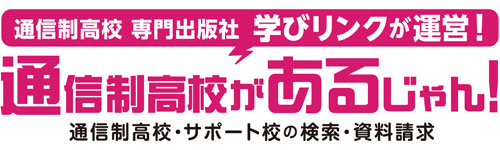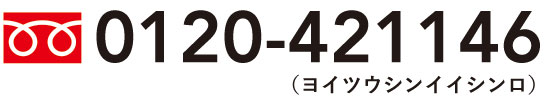椎名雄一先生コラム『不登校に効く心理学の話』61
兄弟姉妹とのバランスが難しいと感じるあなたへ
2025年5月1日
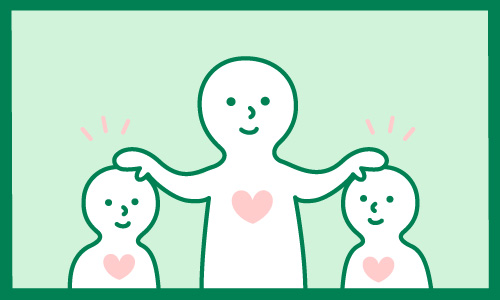 |
ゴールデンウイークなどの長期休暇は家族全体で過ごすことも多いですね。そんな中で特によく耳にするのが「兄弟姉妹とのバランスが難しい」というお悩みです。不登校のお子さんに気を取られすぎてしまい、他の兄弟が拗ねてしまったり、上のお子さんに下のお子さんが振り回されたり、場合によってはストレスのはけ口になってしまうこともあります。
親が「平等に接している」と思っていてもそれが子どもたちの主観と一致しているとは限りません。
悩んでいる時には人は「自分の側100%で接して欲しい」と感じるものです。「双方の意見を尊重して」「相手にも事情がある」などという五分五分でバランスの取れた「平等」など受け入れられません。そうなると親が仮に90%味方をして10%他の兄弟というふうに関わったとしても「足りない。自分はどうでもいいんだ!」と解釈されてしまいます。
兄弟の問題に向き合う時には主観的な解釈がどうなっているかが大事なので「平等」ではダメだということはまず押さえておきたいところです。「自分の側100%」で初めて安心するような傾向があります。
その主観に合わせる時に大事なのは「分割する」ことです。
簡単なものから3つご紹介すると
1つ目は「時間」を分割することです。
上のお子さんと下のお子さんと別々の時間に1:1で接することができたらそれはチャンスなのでその時には「兄弟」や「関係ない人の話」をせずに、そのお子さんの好き嫌いや価値観に寄り添って100%(できれば120%)の反応ができると良いです。
120%というのは「それは嬉しいけれどそこまではやらなくてもいいよ」とお子さんが思うような返しを織り交ぜるということですね。お子さんが「誰かに嫌なことを言われた」と話してくれた時に「それは嫌だったね」という応対が100%だとしたら「もうさ、そういうこと言った人はやっつけないといけないね!」「いやそれはやりすぎでしょ」というような冗談半分で過剰反応をしてみると120%のようになります。
過剰であるからこそ、相手ではなく完全に自分の側に立ってくれているという印象になりやすいので、「味方だよ」アピールをする時に参考にしてみてください。ユーモアを混ぜるのがコツです。
2つ目は「テーマ」を分割すること。
「ゲーム好き」な上の子と「鉄道好き」な下の子がいたとすれば、話題を切り替えることで「自分の番だ」となりやすく、話題を上手に切り替えれば「鉄道」の話に上の子が介入してくることもないので安心して自分の話題で話をすることができます。家族で一緒に過ごすときなどはテーマを順番に選ぶことで満たされやすくなります。
その2つ目を成立させる意味でも大事なのは3つ目です。
3つ目は「価値観」を分割することです。
兄弟といっても価値観が違います。「集める」のが好きな子も「分析する」のが好きな子もいます。
学びリンクの保護者ラボ(ほごらぼ)ではお子さんは「名詞」ではなく「動詞」で見極めようというノウハウが一般的ですが、お子さんの心を動かす動詞をそれぞれに見つけていれば、その動詞を中心に関わることでそのお子さんの大事にしていること、つまり価値観にフォーカスすることができます。上のお子さんは「集める」話題、下のお子さんは「分析する」話題という守備範囲を意識することによって、お互いが同じ基準で競わなくて済むようになります。上のお子さんは「たくさん集めたね」「コンプリートじゃん」「これはレアだけれどよく手に入ったね」のような関わり方が大事ですし、下のお子さんは「なるほどこうなっているんだ」「分析力が半端ないね」「分析してもらうとよくわかる」といったリアクションが良さそうですね。
自分に光が当たる領域が理解できているといわゆる自己肯定感、自己効力感が上がっていきますので、兄弟と比較して落ち込んだり、拗ねてしまうことが減ります。
企業では一般的なことでもありますが、いくつもの評価基準を設けて、それぞれの個性に合わせて目標設定、モチベーションを上げていく工夫ができます。「学校に行けること」を基準にすればどちらがちゃんと行っているか?だけで競うようになるのでうまくいきません。
ぜひ参考にして、兄弟がそれぞれ良い未来が見えるように活用してください。