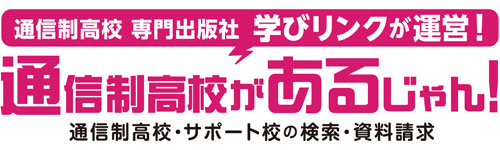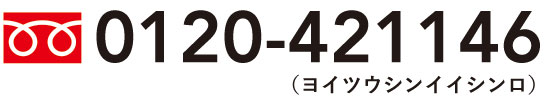椎名雄一先生コラム『不登校に効く心理学の話』64
子どもの将来が見えなくて不安になる
2025年7月9日
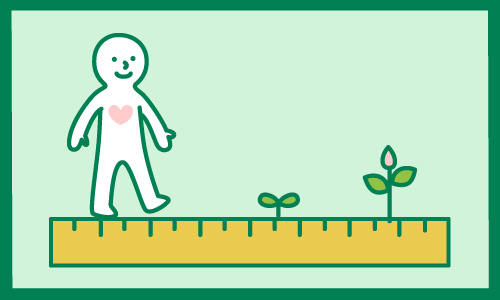 |
夏休みが近づくこの時期、焦ってしまう保護者の方が多いのではないかと思います。周りの子たちが進路の話をし始めたり、受験に向けて塾に通い出したりすると、「うちの子はどうなんだろう」「このままで大丈夫かな」と不安になってしまうのは、当然のことです。
私もこれまで多くの保護者の方から、こんな声をいただいています。
「進路の話をしようとすると、本人が部屋から出て行ってしまうんです」
お子さんの将来を考えたくなるのは、親として自然なこと。でも、子ども自身がその話題を受け止める準備ができていないと、話そうとしてもなかなか進まないんですよね。部屋から出て行ってしまうのは、嫌がっているわけではなく、まだその話を受け止めきれないだけかもしれません。
こんな時こそ、「焦らない」のは大事です。
焦る気持ちはわかります。夏休みが近づくと、何かしら「次のステップ」を踏まなければいけないような空気が出てきます。でも、そこはぐっと堪えてください。「焦らない」のが大事です。
実際に、学びリンクの保護者ラボ(ほごらぼ)に参加されている方々からも、こんなお話をよく伺います。
「最初は学校に戻ることばかり考えていたけれど、学校より先に人生を充実させようと思ったら、家の中の雰囲気が変わりました」
そう気づけると、親子の関係がとても穏やかになります。お子さんもプレッシャーから解放されて、自分のペースで進み始めるんですね。考えるべきなのは「学校どうするか?」ではなく「人生どうするか?」だからです。人生と向き合っていないのに「学校どうするか?」は決められませんよね。学校は「便利な道具」であって、人生でも進路でもないからです。
「焦ってしまう方」は遠い未来を見ています。「1年後大丈夫かしら」「生きていけるかな?」それも大事ですが、そこに繋がるためにはそれが現在と繋がっていないといけませんね。
でも、未来は『今この瞬間』の積み重ねでできています。
将来がどうなるかは、誰にもわかりません。でも、今日お子さんと何気ない会話をしたり、一緒にごはんを食べたり、笑い合ったり、、、そんな小さな行動が、確実に未来に繋がっていきます。
進路の話ができなくても、今は、お子さんが安心できる環境を一緒に作っていきましょう。逆にあいさつや日常会話ができていないのに進路の話をする人がいますが、皆さんはあいさつもできないような疎外感がある会議や組織で「どうしたいですか?」と聞かれたら答えられますか?怖くて何も言えなかったり、何で自分が答えないといけないの?と思うかもしれません。
人はそこに参加しているから意見を持ちます。
参加して、「こうしたいな」「これがかっこいいな」「これ面白そうだな」という小さな体験と感想の積み重ねで「自分だったらこうしよう」というのが出てきます。その第一歩は家の中で家族と何かを共有することです。
進路というのは唐突に10km先に出現するものではなく、1mm先1cm先の出来事の延長にあります。
今この瞬間のお子さんが「おはよう」と明るく挨拶をする。夢中になって、学校以外のことに熱中する。「不安がある」と言って自分自身の人生を振り返ったり、反省・改善しようとしている。そこに目を向けると芽が出始めていることに気づけるのではないかと思います。
将来はその芽を育てた先にあります。繰り返しますが、唐突に10km先に出現するものではないのです!