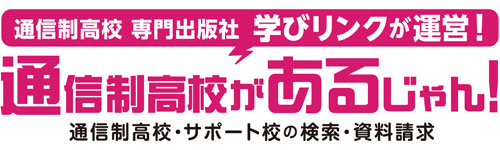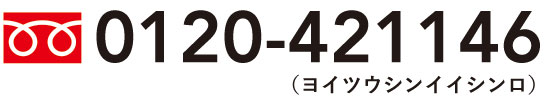椎名雄一先生コラム『不登校に効く心理学の話』65
お子さんの自己肯定感の高め方
2025年7月18日
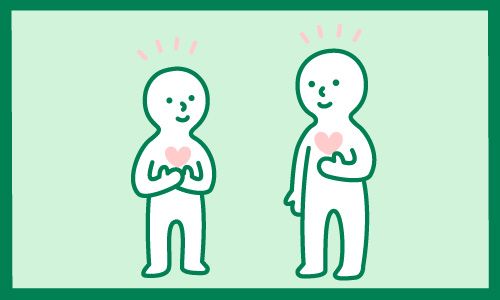 |
近年、「子どもの自己肯定感」「親の自己肯定感」という言葉をよく耳にします。
自己肯定感が低いので学校に行きにくかったり、普段から緊張してしまったりする。だから、自己肯定感を高める方法はないか?という質問も多くあります。
自己肯定感とは
「自分を大事だと思える感覚」のような意味です。
承認欲求のように「誰かに褒められるか?」「誰かに認められるか?」ではありませんね。
自己効力感のように「これができるかどうか?」でもありません。
できるできないとか褒められるかとは関係なく「自分を大事に思えるか?」です。
そう考えると
昨今の褒めすぎる子育ては承認欲求ばかりを伸ばしてしまい、自己肯定感が育ちません。きつい言い方をすると対して何もしていないのに「褒めて欲しい」「目立ちたい」という子が増えてしまいます。
では肝心の「自分を大事だと思える感覚」はどうやったら育つのでしょうか?
私たちが何かを大事だと思う時にはある傾向があります。
それは「そのもの」「その役割」「その人」などに対して、時間と労力、お金などをかけているかどうかです。なんの特徴もないただの手帳でも10年使い続けてきたら「かけがえのない手帳」になります。「大事だと思える感覚」が芽生えます。スマホを「かけがえのないもの」と思っている人が多いのも同じ理由です。スマホに対して時間と労力、お金などをたくさんたくさん費やしているからです。
子育てもそうです。一般的にお腹の中にいる時から赤ちゃんの時期、子どもが大きくなるまでずっと一緒にいて、いわゆる時間と労力をかけ続けているのはお母さんです。仕事に行っていて、お子さんと関わる時間が少なく、労力も費やしていないお父さんがいたとしたら、驚くほどの差ができてしまいます。だから多くの場合、お父さんと比べて、お母さんの方が「我が子がかけがえのない存在」という感覚が強いのです。
それが「何かを大事だと思う感覚」と繋がっているとしたら、自己肯定感はどうなると思いますか?承認欲求ばかり気にして、人の顔色を伺い、表面的なアピールで反応を得ようとしていたら自己肯定感は高まりません。ゲームなどに時間と労力を割いて、風呂キャンセル、歯磨きキャンセルというような生活では自己肯定感は高まりませんね。それはそもそも「自分を大事にしていない」からです。
自己肯定感とは自分自身に時間と労力をかけることから始まります。わかりやすい例を挙げれば、筋トレとかダイエットに取り組んで、ある程度結果が出てくると自己肯定感が上がります。それは自分自身に対して、時間と労力をかけているからです。
自分自身とした小さな約束を守る。
自分自身で自分の身の回りを整える(部屋を片付けるなども)
自分が自分を認められるような行動をする。
自分の将来や健康、成長につながりそうな行動をする。
信頼できる人間関係において「ありがとう」といわれる居場所を作れている。
などは自己肯定感が上がりやすいポイントと言えます。
行動していないのに褒められても自己肯定感は上がりませんが、行動したことに「ありがとう」と言われれば自己肯定感が上がります。「自分のことが好きになれる行動」を少しずつ積み重ねていくことが自己肯定感を高めることにつながります。
保護者の自己肯定感という観点で言うと自己肯定感とは「自分」の話なのに「お子さんのため」というテーマを中心にしている時点で話がずれています。親は「お母さん」という側面もありますが、「会社員」「趣味の仲間」など別の側面も持っています。親の自己肯定感は子どもが成功したら上がるのではなく、自分自身の人生を前に進めたら上がります。「あなたのため」とお子さんを中心にしたゲームをプレイしている間は自分の人生と向き合っていないことが多いので自己肯定感は上がりにくい傾向にあります。
親も子も自分自身に対して、自分自身の人生に対して、時間と労力をかけて大事にすることで自己肯定感が高まりますので、そういう時間を確保しておくことはとても大事なことです。
ぜひ参考にして、兄弟がそれぞれ良い未来が見えるように活用してください。