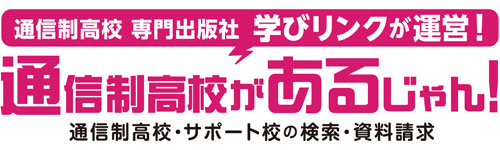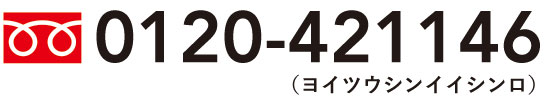椎名雄一先生コラム『不登校に効く心理学の話』66
「気持ちを落ち着けてから」子どもと向き合うために必要な心構え
2025年9月1日
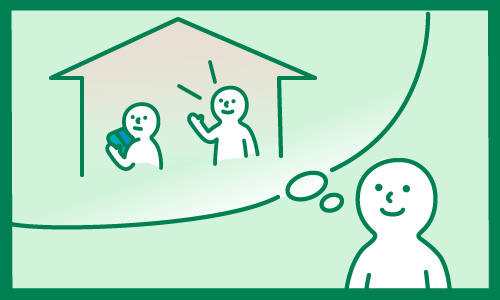 |
日々、保護者の皆さんからのご相談を受ける中で、子どもとの接し方に悩む声を多くいただきます。その中でも特に多いのが「つい感情的に叱ってしまう」「落ち着いて話せない」というものです。「いつも句読点まで待てずに口を挟んでしまう」という人もいます。
今回は、子どもと向き合う際に大切な「気持ちを落ち着けてから関わる」という姿勢についてお話しします。
不登校の子どもを前にすると、保護者の皆さんは「どうして学校に行かないの?」「このままで 大丈夫なの?」と不安になります。その気持ちが強いあまり、つい「早くしなさい!」「いい加減にして!」と感情的な言葉を投げてしまうこともあります。そのお気持ちはお子さんを心配する親としては当然のことですが、子どもにとってはプレッシャーとなり、心を閉ざしてしまう原因にもなります。
大切なのは「子どもの立場に立つ」視点です。
例えば夕飯時「ご飯だよ!」と呼んでも子どもがすぐ来ないのは、友だちとのオンラインゲームの途中かもしれません。そんなとき「何してるの!」と強い口調で言われると、「自分の事情を理解してもらえない」と感じてしまうのです。
落ち着いて関わるためには、まず自分の気持ちを整えることが第一歩です。
大袈裟なやり方ですが、いったん家の外に出て、家全体が見えるくらいまで下がって家を眺めてみてください。そして、その家が誰か他の人の家であるかのように想像してみてください。その中には「ご飯だよ」という母がいて、オンラインゲームをして部屋にいる子どもがいる。通りすがりの人のような気持ちでその様子を想像したら、どんなふうに関わるのが良いでしょうか? 少しイメージが変わるかもしれませんね。少しだけ冷静になれると思います。
思春期のお子さんの場合、特に強い言葉に敏感です。「また怒られる」「どうせわかってくれない」と感じやすい時期だからこそ、落ち着いたトーンで話しかけた方が伝わりやすくなります。特に小学生の低学年のお子さんにはより具体的に「このゲームが終わったら一緒に食べよう」と提案してあげると理解しやすくなります。
「ゲームばかりしている」という悩みもよく聞きますが、その中で友だちと協力したり目標を達成する経験をしていることもあります。「どんなゲームなの?」「どんなキャラを使っているの?」と興味を持って聞くことで、子どもも安心して自分を表現できます。そして、ゲームの概要やお子さんにとっての大事なポイントを押さえているからこその関わり方ができます。
「早くしなさい」より「キリがいいところで」の方が良いですし、「次のマッチングで」の方がより理解されている気がしますね。そして、最近はボイスチャットなどで繋がっていることもありますので、大声よりもLINEがいいですね。LINEで「早くしなさい」とメッセージを打つのと、お子さんが好きな推しのスタンプで「ごはんだよ」と打つのではどちらがお子さんが動いてくれそうですか? ちょっとした工夫でもだいぶ雰囲気が違いますよね。
子どもとのコミュニケーションはそんな「親の雰囲気」「家の雰囲気」で決まると言っても過言ではありません。不安や焦りではなく、信頼と安心感の雰囲気を作ることが大切です。そのために、まずはご自身の気持ちを整えることから始めてみてください。気持ちが整っていないとお子さんにあった伝え方ではなく、こちらの気持ちをぶつけるようになってしまいます。どのスタンプがいいかな? と選ぶ余裕が欲しいですね。
学びリンク主催の保護者会(ほごらぼ)はそのために活動しています。
保護者は理不尽な状況の中でたくさん工夫して、たくさん我慢しています。それがお子さんに染み出して行かないようにするためにも保護者同士で助け合っていくための場です。ぜひそちらを活用しつつ、お子さんには冷静に向き合うようにしてみてください。