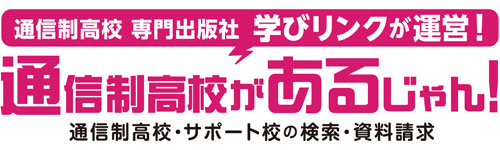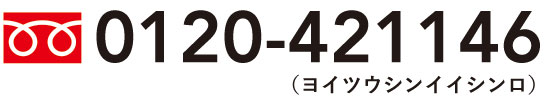椎名雄一先生コラム『不登校に効く心理学の話』67
「教える」「教わる」親子関係の新しい形
2025年9月10日
 |
保護者の皆さんからのご相談を受ける中で、「子どもが何も話してくれない」「どう関わったらいいかわからない」というお悩みをよく聞きます。その一方で、子どもからは「お母さんはいつも怒ってばかり」「話す気になれない」といった声も耳にします。今回は、子どもとの関係を深めるために「教える」「教わる」という視点を取り入れる大切さについてお話しします。
多くの保護者の皆さんは、子どもを育てる立場として「教える側」「導く側」でいることに慣れています。「宿題は?」「早く寝なさい」「こうしなさい」「もっと頑張りなさい」...。もちろん、教えることは親の役目の一つです。しかし、子どもにとっては、親に教えられるばかりの関係は窮屈に感じることがあります。一方的に「教える」関係ではなく、ときには「教えてもらう側」に立つことで、子どもは自分が認められていると感じ、心を開いてくれるようになります。
例えば、お子さんが熱中しているゲームや趣味のことを「教えてほしいな」と頼んでみるのです。
「このキャラクターは誰なの?」「どうやったら勝てるの?」と素直に聞いてみると、子どもは嬉しそうに話し出してくれます。保護者が生徒になり、子どもが先生になる。この関係性の逆転が、子どもの自己肯定感を高める大きなきっかけになります。
以前、あるお母さんが息子さんにオンラインゲームの操作方法を教わったところ、会話が増えただけでなく、息子さんが「俺も役に立つんだな」と自信を持つようになったという話もありました。
思春期のお子さんの場合、特に親からの指示や説教を嫌がる傾向があります。「また怒られる」「どうせ理解してもらえない」と壁を作りがちです。そんなときこそ、「教えて?」と言われると意外なほど心を開いてくれます。高2のお子さんからは「俺が説明したことをちゃんとメモしてる親を見て、少し誇らしかった」という声も聞きました。こうした小さな体験が、思春期の複雑な心を溶かす糸口になります。
小学生のお子さんなら、「このポケモンの強さってどうやって決まるの?」「折り紙のこの折り方、教えて」など、日常の些細なことで構いません。低学年であればあるほど、「自分のことを見てくれている」という感覚が大切です。年齢に応じて、子どもが得意なことや好きなことを教わる姿勢を見せることで、自然に信頼関係が育まれていきます。
注意してほしいのは、教わる時には良い生徒であることです。内容についてマウントしない。一度言われたことはメモをして忘れない。関連情報などをちゃんと復習する。などは師匠と弟子の関係では当然のことです。突然自分が知っている知識で上書きし始めたり、何度も同じことを聞く弟子はダメな弟子ですよね。お子さんの教え方を尊重し、当然拙い説明だったり、わかりにくいこともあると思いますが、伝えてくれようという気持ちを大事にしてください。大切なのは知識の正しさではなく、「あなたの話をちゃんと聞いているよ」という姿勢です。
この「教える・教わる」という両面の関係を意識することで、子どもとの会話の雰囲気はぐっと柔らかくなります。保護者の皆さんが聞き役に回ることで、子どもは「自分にも価値がある」と感じ、親に対しても優しい気持ちを持てるようになります。あるお母さんは「息子にスマホアプリの使い方を教わってから、毎日話すきっかけが増えました」と笑顔でお話しされていました。
そんな小さな積み重ねが、信頼を育むのです。
そして、社会においてこの二面性はとても大事です。「お客さんと店員さん」両面から見える人は横柄な態度を取ったり、お店を不必要に汚したりしません。店員さんが困ることを知っているからです。
「生徒と先生」両面から見える人は誰かの話を真剣にうなづきながら聞きます。自分が聞いてもらえないで辛い思いをしたことがあるからです。自分が「教える」という立場をとるからこそ「教わる」価値も「教わる」作法もわかるのです。